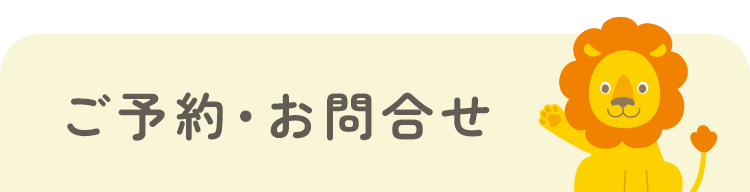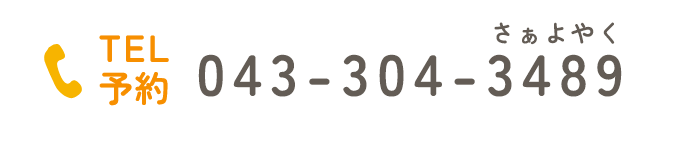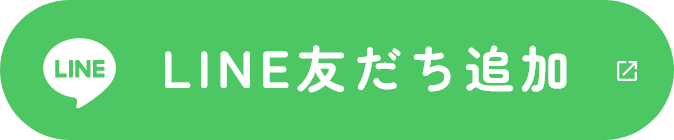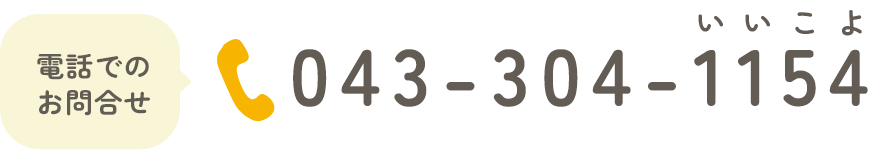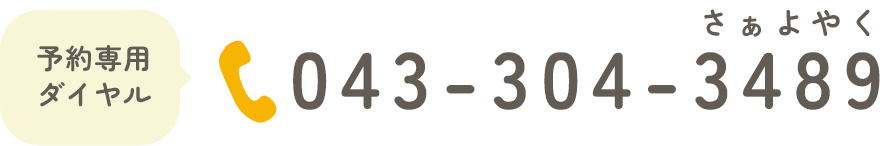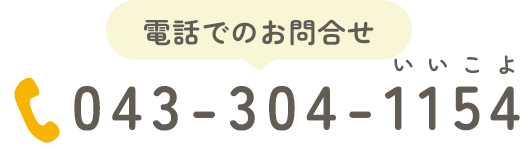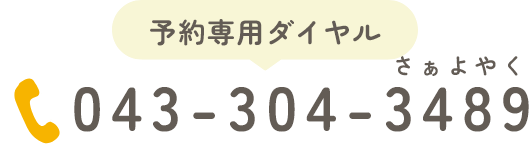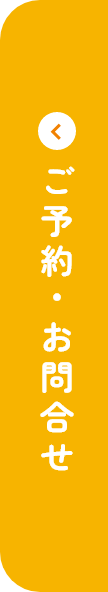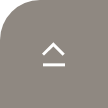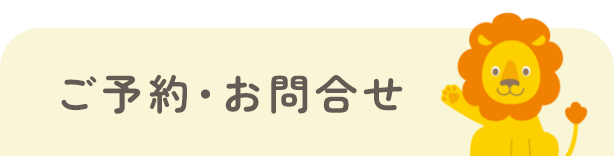『読み書き計算』に困難のある子どもたちへの支援について 2
以前『読み書き計算に困難のある子たちへの支援について1』で自分を知って利用できるものを活用しようと書かせていただきましたが、いかがでしたか?
「うちの子は関係ないな」と思われた方が多くいらしたかもしれません。では、もし、学校のテストをPCを活用して漢字の変換をしたり、計算をさせたりしている子がいたらどう思われますか?受け入れることはできますか?
特定の子どもだけがICT(情報通信技術)を活用することに不公平を感じる方もいらっしゃるだろうし、子どもの中には、一人だけ違った形で学ぶといじめられるなどの心配から、困難を抱える子ども自身がICT活用を拒否する子もいます。
現在、幸いにも学校・企業・団体に「合理的配慮」の提供が義務付けられ、困難さを補うICTの活用が法的に守られています。実際に、配慮の申請をし入学する学生が2023年度には全学生数の1.79%ととなり、10年前から比べると4倍に増加しました。
ただ、サポート人員と体制の圧倒的不足や、硬直化して柔軟性に欠ける学校ルール、子どもが安易にテクノロジーに依存することが危険であるという意見など、困難を抱える子どもに対する合理的配慮にICTが取り込まれるには、まだまだ高いハードルがあります。
ここで、支援技術機能を紹介します。
読みの困難さに対して:
読み上げソフト 拡大ソフト ルビソフト 辞書 電子図書
書きの困難さに対して:
タイピング 仮名漢字変換 音声入力 カメラ 録音・録画
聞きの困難さに対して:
音声文字変換 ワイヤレス補聴システム ノイズキャンセリングヘッドフォン
計算の困難さに対して:
電卓 電子マネー
記憶想起の困難さに対して:
メモ 録音・録画
思考整理の困難さに対して:
マインドマップ 生成AI
予定管理の困難さに対して:
スケジューラ タイマー アラーム
感覚過敏の困難さに対して:
ノイズキャンセリングヘッドフォン、ヘッドマウントディスプレイ
注意の困難さに対して:
リマインダー ワイヤレス補聴システム ノイズキャンセリングヘッドフォン
地誌感覚の困難さに対して:
ナビゲーション GPS
対話の困難さに対して:
電子メール SNS オンライン会議システム
私もすべてを把握しているのではないのですが。
実際、四街道市で導入されているのは「読み上げソフト」「カメラ」です。先生から打診はないと思うので、必要だと思われる方は、粘り強く申し出なければなりません。
導入が簡単でいいなと思うのは「ワイヤレス補聴システム」です。先生にマイクをつけてもらって対象の子どもはイヤホンをつける形式です。
時代は変化し、語学力がなくともスマホの言語変換機能を通して会話ができるようになりました。また、生成AIを使用して自分の考えを文章化できるようにもなりました。
能力を排除するのではなく、補い合いながら一緒に生活できる社会が住みやすい社会だと思うのです。